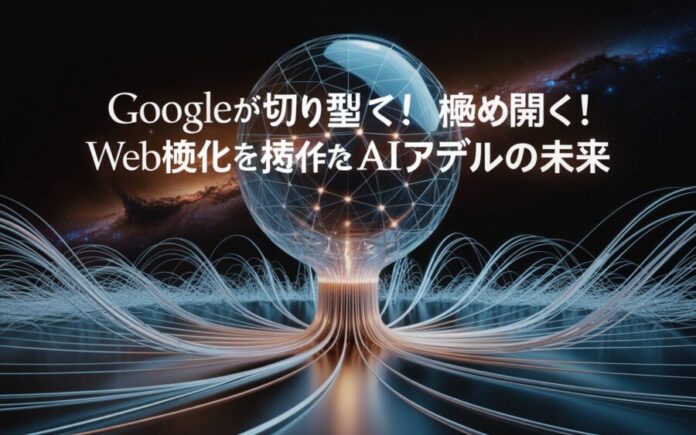Googleが2025年10月にプレビュー公開した「Gemini 2.5 Computer Use model」は、Webサイトの操作に特化した新世代AIモデルとして、人工知能によるWeb体験を根本から革新しようとしています。この「特化型AIモデル」は、単なる情報検索や自然言語による質問応答だけではなく、ユーザーの指示に応じてWebページ上の実際の操作——例えば、クリックやスクロール、フォームへの入力や送信など——を自動的に実行する能力を備えています。こうした機能はビジネス領域のみならず個人の生活にも多大な影響を及ぼし、Web操作の未来を大きく切り開くものとなるでしょう。
特化型AIモデル「Gemini 2.5 Computer Use model」の特徴
本モデルの最も大きな特徴は、「WebサイトのUI(ユーザーインターフェース)と直接対話できる」点にあります。これは、AIが人間のように画面を見て、何をクリックするか、どこに文字を入力するか、ボタンを押すなど、一連の操作を独自に判断し、実際に動作まで行うということを意味します。
Gemini 2.5のコア機能は「computer_use」ツールとしてGemini APIに統合されており、開発者はこのAPIを利用して以下のようなAIエージェントを容易に構築可能です。
– 画面上の状況をキャプチャ(例:スクリーンショット)
– 直近の操作履歴を取得
– ユーザーのリクエストを解析
– 必要なUIアクション(クリック/文字入力/スクロールなど)を関数呼び出しとして返却
この仕組みにより、Gemini AIエージェントは“人間の代理”としてWebアプリケーションや各種サービスの操作を自律的に進めていくことができます。
利用シナリオとインパクト
Gemini 2.5 Computer Use modelによって実現できるAIエージェントは、多岐にわたる業務やサービス自動化の未来像を描きます。
– 業務自動化: 企業内での経費精算、CRM(顧客管理)、SaaSアプリの設定変更など日常的な“ルーチン作業”をAIが代行可能。
– カスタマーサポート: チャットボットがWeb上で問い合わせ内容を受け付け、必要な手続きを自動化して利用者の満足度を向上。
– eコマース: 商品検索から比較、カートへの投入、注文確定までの一連の流れを、ユーザーの好みや過去データをもとにAIが最適化しながら自動実行。
– アクセシビリティ支援: 高齢者や障がい者をサポートするAIエージェントが、複雑なWebサイト操作を全自動化し、ITバリアフリーを推進。
さらに、Googleが同時発表した「Gemini Enterprise」では、Google Workspaceなど基幹クラウドサービスやサードパーティ製ソフトと連携し、あらゆるビジネスシーンでWeb操作を軸としたAI自動化が進む構想となっています。
技術的なブレークスルー
Gemini 2.5の技術的進化で注目すべきなのは、「Webページの構造把握」と「ダイナミックな推論エンジン」の融合です。AIは、画面そのものを画像情報として取得し、そこからHTML構造やUIの文脈を自動的に理解、指示された目標に基づいて最適な手順を推算していきます。この過程は、従来のRPA(Robotic Process Automation)が持つ「静的な手順の自動化」から、「ダイナミックかつ柔軟なタスク遂行」への大きなジャンプです。
具体的には、ユーザーが「このサイトで資料をダウンロードしてほしい」と入力すると、Gemini AIが画面を観察し、該当リンクの特定からダウンロード実行、必要に応じたログイン・フォーム記入・認証を自動で行えます。こうした「人間のような推論力」と「操作技術」の融合が、Webの自由度を大きく拡張する原動力となっています。
今後の展望と課題
特化型Web操作AIモデルの今後は、さらに高度な人間協調作業や複数サービス横断の自動化、ユーザー環境への適応性向上など多くの発展が見込まれます。
– セキュリティとプライバシー: ユーザーの個人情報や業務データへのアクセス拡大は、セキュリティ対策と利用ガイドラインの厳格化を不可欠にします。今後はガバナンスと技術的防御の融合が求められます。
– インターフェースの多様化: 音声操作やAR/VRと連動したインターフェース拡張により、AIのWeb操作は“見えない操作パートナー”として日常にとけ込んでいく可能性があります。
– Webエコシステムの進化: ページ内の構造や権限制御、API連動の発展で、AIとWebサービスのシームレスな協調が加速。今後は“AIフレンドリー”なWeb設計も進展するかもしれません。
GoogleのGemini 2.5 Computer Use modelは、「Webを操作できるAI」という新次元の価値軸を創出し、これからのデジタルトランスフォーメーション(DX)と社会全体の生産性変革を強力に後押しする存在となるでしょう。