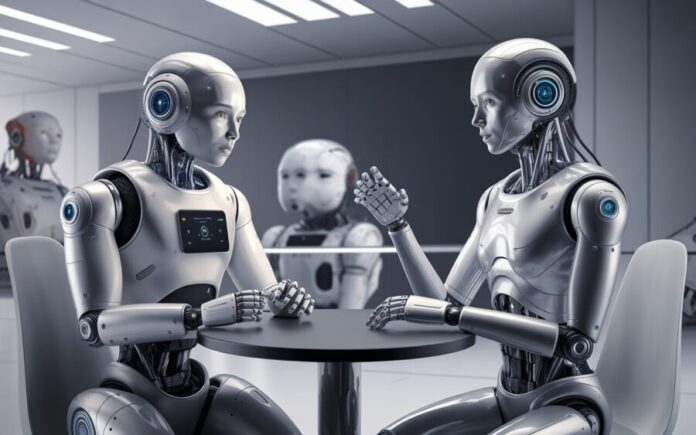新しい共創を拓く生成AIモデル:ChatGPTからGeminiまでの進化と実践
2023年以降、生成AIモデルは「創造」と「共創」の概念に真の変革をもたらしました。ChatGPTに始まり、GoogleのGeminiなど多様なマルチモーダルAIが登場したことで、単一ユーザーによるアウトプット生成から、複数の人や組織、AIエージェント同士の“共創”へと進化しています。本記事では、最新の事例を元に、生成AIがもたらす新しい共創の形について詳しく解説します。
—
■ マルチモーダル生成AIによる共創の拡張
2025年の現在、生成AIは「テキスト」や「画像」だけでなく、「音声」「動画」など複数メディアを横断的に理解・生成できるマルチモーダル型へと進化しています。この技術により、デザイン、文章、映像、音楽といった異分野の専門家同士、あるいは人間とAI、さらにはAI同士が協働し、“人間のみでは生み出せなかった創造”が次々に実現。たとえば広告分野では、マーケター・デザイナー・AIがリアルタイムでアイデアを出し、ターゲットに最適化された動画広告が数日で制作され、テスト配信や効果測定もAIが自動で補助する――こうした流れが標準化しました。
—
■ デザイン現場におけるAI共創の鮮明な変化
特にWEBデザイン制作では、Adobe CreativeCloud等の従来デザインツールと高度に統合されたAIスイートが台頭。クリエイターが持つ課題や要望、コンセプトの方向性をAIが理解し、プロトタイピング~最終アウトプットまで一貫した創作支援が可能になっています。AIは膨大な市場・消費者データから最適化提案を繰り返し、ユーザーごとにパーソナライズ化されたインターフェースが即応生成されるため、従来の「発注」と「提案」「修正」の重複・手戻りが激減。これにより、デザイナーは“感性や発想の深堀”に集中できるようになっています。
顕著なのは、これまで困難だった「リピート顧客への最適化」や「細やかなUI調整」もAIの学習と生成能力で“自動化+最適化”され、結果として顧客の滞在時間・コンバージョン率・リピート率すべてが向上しています。
—
■ 多様な業界・社会課題×生成AI=共創の実装へ
生成AIによる共創の波は、製造・医療・自治体・金融など多様な業界へも広がっています。2025年に公開された生成AI活用事例データベースには、国内18業界・1008件超の生成AI活用実績が集約。たとえば製造業現場では、設計者・エンジニア・AIがチーム単位で製品アイデア→設計→試作→改善まで高速にサイクルを回す。医療分野では多職種(医師・看護師・経営層)+生成AIによる治療計画策定や説明資料作成。自治体では住民参加型のまちづくり合意形成支援など、実演レベルで共創が定着しつつあります。
単なる「AI導入」ではなく、“AIもひとりのメンバー”として人間と対等に議論し、状況・感情・意図を推し量りつつ最適な提案をしてくる――この姿が新しい日常となりつつあります。
—
■ 法制度・運用体制の充実と「信頼できる共創」へ
AIと共創した成果物が社会に広く流通する中で、AI Act(EU)や日本の「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」といった法整備が急ピッチで進行。生成物のAI活用の明示義務や、著作権・データ利用の透明性確保、クリエイターへの対価還元指針などが規定され、単なる技術主導ではなく“人とAIが安心して共創できるルール”が整い始めました。
—
■ これからの創造:共創の文化とAIリテラシー
2025年現在、Society5.0時代と呼ばれるデジタル社会のなかで、生成AIモデルは産業界のイノベーションのみならず、“市民一人ひとりの創造性の共創パートナー”へと役割を広げています。
今後は、AIと共にアイデアを生み、他者と意見を重ね合わせ、技術・表現・社会課題を超えた共創・協働の“文化”そのものが一層進化していくでしょう。
生成AIとの共創は「人の創造性を拡張・解放」し、「新しい価値を社会実装するエンジン」として、今まさに加速度的に発展しています。