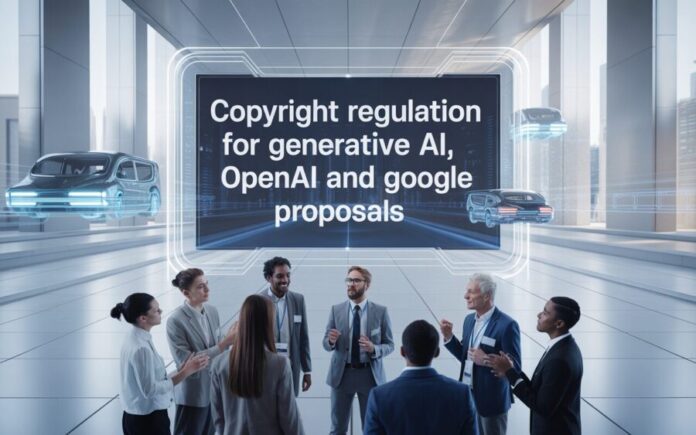2025年に入り、生成AIの活用を巡る著作権規制のあり方が世界的な議論の中心となっている。特にOpenAIやGoogleといった米国の主要テクノロジー企業は、AIのさらなる進化と社会実装の促進を目指して、著作権規制の緩和や適用範囲の見直しを積極的に提言している。一方で、クリエイターや権利者団体、報道機関からは懸念や反発も強く、現行制度のままAI開発の自由を拡大することへの慎重論も根強い。
現状、多くの生成AIモデルは、著作権で保護された書籍、音楽、画像など多種多様なデータを訓練に利用している。これまでAI開発者側は、訓練段階での著作物利用が「フェアユース(公正利用)」や、事実情報の活用であって完成品の著作物再現ではないことから「変容的利用」などと位置付け、権利侵害には当たらないと主張してきた。しかし最近は、AIによる生成物が原著作物と類似性が高くなったり、オリジナル作品の市場と競合するといった実例が増え、著作権者側が損害を受けるリスクが明確化しつつある。
その流れを受けて、OpenAIやGoogleをはじめとするAI企業は、生成AIの研究開発および社会実装の加速には「学習データへのアクセス確保」が不可欠であると主張し、以下のような著作権規制の緩和や法改正案を提示している。
– インターネット上のコンテンツを、オプトアウト申請がない限りAI訓練データとして利用できる「包括的利用」
英国政府はその具体的な法改正として、現行では禁止されているAI訓練目的の著作物利用について、原則許容(オプトアウト制)の方向性を示唆。これに対しOpenAIやGoogleも、学習データの可用性向上がAI技術全体の発展につながると賛同している。
– フェアユースの範囲拡大・国際調和の推進
ヨーロッパでは比較的厳格な著作権運用がなされているが、米国流のフェアユース拡大を唱え、世界的なルールの調和と技術発展の両立を模索している。
– 「変容的利用」との区別強化
AI生成物が原著作物の「単なる複製」ではなく、明確に新たな内容や表現を生み出すこと、訓練データの使用が市場的に直接競合しない場合は利用を認めるべきとする提言を示した。
こうした主張の背景には、AI産業における「データの質と量」の確保が国際競争力を左右するという危機感がある。特に2023年以降、米国や中国を中心に巨大な言語モデルや画像生成AIの開発が加速しつつあり、著作権法の枠組み内でいかに円滑に訓練データを調達できるかが、技術革新のボトルネックになっている。OpenAIやGoogleは、「公共の利益」を前面に出し、一定のコンテンツ利用を認めることで社会全体の知識や創造性が向上すると訴えている。
一方で、こうした規制緩和の提案に対しては、クリエイターやメディア業界を中心に反発も強い。たとえばイギリスでは、個人や小規模の権利者が自身の作品について「オプトアウト」を申請する負担が大きく、事実上AI企業が使いたい放題になるとの指摘がある。また、画像生成AI「Midjourney」が既存の著作物に酷似した画像を大量に生成できることや、言語モデルが新聞記事の要約・転載を通じてメディアの収益を奪う事態が顕在化しつつある。フランスではGoogleが報道コンテンツの利用料支払いを巡って数百億円規模の制裁金を受けるなど、既存の産業構造や公正な競争環境への懸念も強まっている。
さらに、議会や政策当局のなかでも意見が分かれる。英上院では、権利者が「積極的に同意(オプトイン)」しない限りAI学習への利用を禁止すべきという案が提起されており、いかにしてバランスの取れたルール設計を行うべきかが問われている。
今後、OpenAIやGoogleなどが進める著作権規制緩和論と、クリエイターや報道機関の権益保護、さらにはユーザーの利益や社会的正義の観点をいかに調整するかが、各国の立法・政策の大きな焦点となる。国際協調や透明性向上のための議論も急務である。どのような妥協点が見いだされるか、引き続き世界的な注目を集めている。