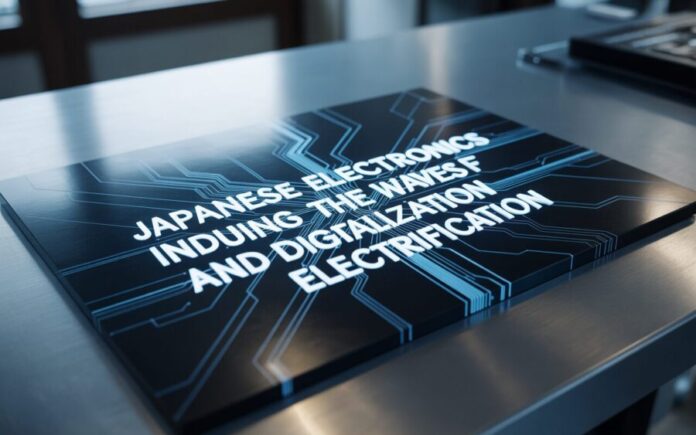日本の電子部品業界は、デジタル化とEV(電気自動車)化という時代の大きな潮流に乗って、急速な変革と成長を遂げつつある。とりわけ自動車の電装化・電動化は電子部品メーカーにとって新たな成長ドライバーであり、今後の産業構造を大きく変えうるキーファクターとなっている。本稿では、EV化を背景に拡大する電子部品の需要と日本メーカーの取り組み、その成長の根底にあるトレンド、今後の課題と展望について扱う。
—
EV化と電子部品需要の急拡大
ここ数年の自動車産業では、脱炭素・環境規制の強化を背景にガソリン車からハイブリッド車、そしてEVへの転換が加速している。電気自動車はモーター駆動のため駆動系統が大きく変化するだけでなく、多数のセンサー、制御ユニット、パワー半導体、大容量キャパシタや電池モジュールなど、従来と比較にならないほど多くの電子部品を必要とする。この変化が、スマートフォンなど既存の大口市場がピークアウトする中で停滞が懸念された電子部品業界に新たな需要をもたらしている。
実際、1台のEVには従来型ガソリン車よりも50%以上多くの電子部品が搭載されるという試算もあり、またその多様化・高付加価値化も進む。例えばパワーコントロールユニット、急速充電対応のパワーデバイス、安全運転支援用のミリ波レーダーやカメラモジュール等、今や一社だけで必要なすべての部品を賄うことはできず、部品の高機能化とサプライチェーンの高度化が同時に進行している。
—
日本メーカーの強みと進化
京セラ、村田製作所、TDK、ミネベアミツミなど日本の電子部品大手は、もともと高い技術力と信頼性を背景に、グローバル自動車メーカーから厚い信頼を獲得してきた。特に以下の点で競争優位性を持つ。
– 高信頼性・高耐久性部品:車載用は高温・揺動等の過酷環境下での長期間安定動作が必須。村田製作所の積層セラミックコンデンサや京セラの電子セラミック部品は、その高耐久性が自動車メーカーに評価されている。
– 小型・高集積化:EVシステムの高性能化・スペース効率化を実現するためには、極めて小さく、かつ多機能な部品が求められる。これに対応した小型電子部品の量産・供給力は日本企業の大きな強みだ。
– 次世代材料の開発力:TDKのような磁性材料の先端技術や、ミネベアミツミの精密加工技術は、パワーエレクトロニクス分野で特に重要だ。
また、電子部品メーカーは需要のグローバル化に合わせて現地生産体制の拡充や、海外売上比率の拡大にも積極的であり、日本発の技術が世界のEVシフトに深く関与している。
—
デジタル化がもたらす製品・サプライチェーンの進化
デジタル化は単なる部品単体の高度化にとどまらず、設計から生産・流通まで産業構造全体に変化をもたらす。代表例の一つが「デジタルツイン」など製造プロセスの仮想化・最適化、そして生産ラインのIoT化・AI化だ。リアルタイムでデータを取得・解析することにより、故障予兆検知や工程最適化、品質改善のスピードが大幅に増している。
自動車メーカーと電子部品サプライヤーがクラウド連携して進める原価低減やリードタイム短縮の取り組みも進化しており、部品の仕様変更・試作サイクルが従来の数カ月単位から数週間単位へと短縮している。
—
成長予測と今後の課題
調査会社の予測によれば、日本の電子部品市場全体は2025年以降も年平均成長率(CAGR)8%超の力強い拡大が続くと見込まれている。この成長の最大要因が、EV・自動運転・5G通信のような新規分野需要の拡大である。
しかし現実には、車載部品の品質・安全規格は厳しく、納入までの認証プロセスが長期化しやすい。さらに半導体材料・重要部材の需給ひっ迫や、グローバルでの地政学リスク(サプライチェーンの分断)など、日本メーカーにとってこれまでにない不確実性も高まっている。
—
展望
デジタル化とEV化の波は今後さらに加速する。日本の電子部品メーカーは、「高信頼・高付加価値」の軸を維持しつつ、①海外拠点強化 ②R&Dへの投資加速 ③脱炭素・省エネ材料開発など、多面的な進化を求められる。その一方で、日本発の部品・材料技術が、カーボンニュートラル社会の実現に不可欠な中核技術であり続けることも確かだ。
今後10年、日本の電子部品業界は世界のモビリティ革命の最前線に立ち続けるだろう。