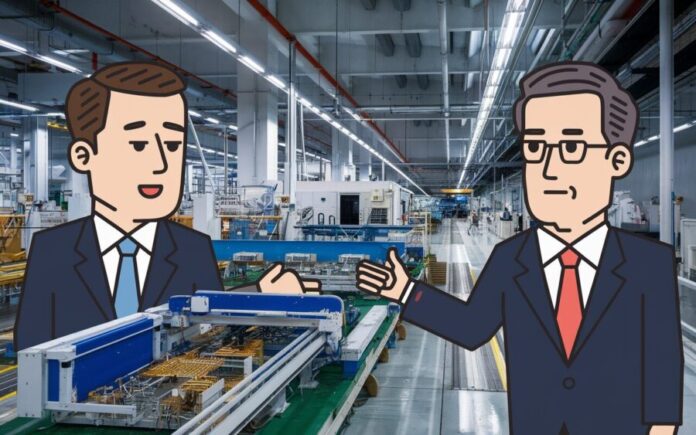日本政府、台湾半導体大手との連携強化で国内製造基盤を拡充
日本政府は、半導体産業の国内製造基盤強化に向けた取り組みを加速させている。その中核を成すのが、台湾の半導体大手企業との連携強化だ。特に注目を集めているのは、台湾積体電路製造(TSMC)の日本進出を支援する大規模なプロジェクトである。
この戦略の象徴的な事例が、TSMCの子会社である日本アドバンストセミコンダクターマニュファクチャリング(JASM)の設立だ。JASMは、熊本県菊陽町に先端半導体工場を建設中で、2024年末の稼働開始を目指している。この工場では、自動車や産業機器向けの12nm~28nmプロセスの半導体を生産する予定だ。
日本政府は、この事業に対して総額1兆円近い巨額の資金を投じている。これは、経済安全保障の観点から重要な半導体の国内生産基盤を確保するという狙いがある。さらに、日本の自動車メーカーや電機メーカーも共同出資で参画しており、産官学連携の新たなモデルケースとして注目を集めている。
この取り組みは、単なる外資誘致にとどまらない。日本企業との協業を通じて、技術移転や人材育成も期待されている。特に、日本が強みを持つ半導体製造装置や材料分野との相乗効果が期待されており、サプライチェーン全体の強化につながると見られている。
また、この戦略は日本の半導体産業復活への期待も高めている。1980年代、日本は半導体製造で世界シェアの5割超を占める半導体大国だった。しかし、その後の国際競争の中で地位を低下させてきた。TSMCとの連携は、日本の半導体産業が世界の最先端に再び追いつき、さらには追い越すための重要な一歩と位置付けられている。
政府は、この取り組みを通じて、次世代半導体技術の開発と製造基盤の確立も目指している。現在開発途上にある2ナノメートル世代の最先端半導体の国産化・量産化に向けた取り組みも進められており、北海道には新たな先端半導体工場の建設も計画されている。
一方で、この戦略には課題も指摘されている。巨額の公的資金投入に対する費用対効果の検証や、技術流出のリスク管理、さらには国内の人材育成など、克服すべき問題は少なくない。また、急速に変化する国際情勢の中で、地政学的リスクへの対応も求められている。
しかし、半導体がデジタル社会の基盤技術であり、今後のAI、IoT、自動運転などの先端技術の発展に不可欠であることを考えれば、この戦略の重要性は明らかだ。日本政府は、この取り組みを通じて、単に製造基盤を強化するだけでなく、イノベーションを促進し、国際競争力を高めることを目指している。
今後は、TSMCとの連携をモデルケースとして、他の台湾企業や海外の半導体メーカーとの協力関係も拡大していく可能性がある。また、国内の半導体関連企業の育成や、大学などの研究機関との連携強化も進められると見られている。
日本の半導体産業の復活と、安定的な半導体供給体制の構築は、一朝一夕には実現しない。しかし、政府主導の積極的な投資と、国際的な連携強化の取り組みは、日本の産業競争力強化と経済安全保障の確立に向けた重要な一歩となるだろう。今後の展開が注目される。