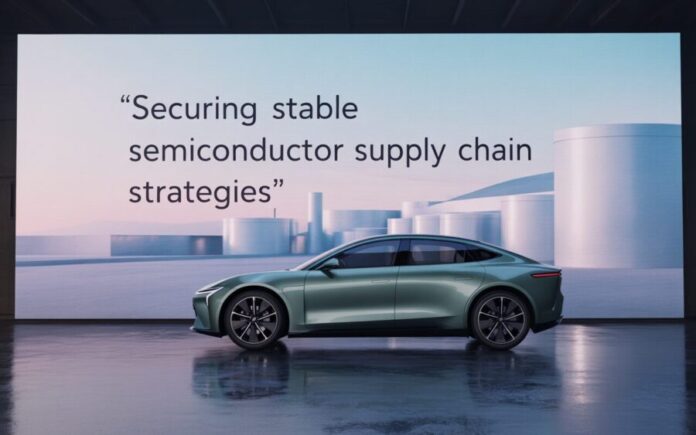日本の自動車産業において、安定した半導体供給を確保するための戦略の中核となっているのが、「日本発・多国間連携と海外資源開発を通じたハイテク供給網レジリエンス構築」である。この戦略は、2020年代初頭の世界的な半導体不足、さらには米中対立によるグローバルサプライチェーンの混乱を経て、急速に進展してきた。
現代の自動車、とくに電動化・自動運転に関連した次世代車両は、多種多様かつ高度な半導体デバイス抜きには成立しない。そのため、安全保障と産業競争力の観点から、単一国や限られた地域への依存を是正し、供給網自体の頑健性を高めることが国家的課題となっている。
日本政府および主要自動車メーカーは、次のような多層的な取り組みを行っている。
■1. 多国間サプライチェーン協調ネットワークの構築
米中対立と半導体戦略物資化の進行を背景に、日本は米国や欧州、インド、オーストラリア、東南アジア諸国などと連携し、「協調ネットワーク」を構築している。これは、単独の国や企業に過度に依存せず、信頼できるパートナー間での取引・技術協力枠組みを厚くするというものである。
具体的には、日本の政府系ファンドによるオーストラリアのレアアース鉱山への出資や、豪州・インドとのレアメタル、リチウム等の調達プロジェクトの推進、中国以外からの鉱物・材料調達ルートの開発などが進められている。さらにアフリカでも欧米と協力し、コバルト等の重要電池素材を持続可能な形で調達する枠組み作りを進行中である【1】。
■2. 国産半導体メーカー・海外大手との連携強化
トヨタやホンダなど自動車各社は、日本国内における先端半導体の生産強化を後押ししている。代表的な事例として、政府・産業界が支援する次世代半導体ファウンドリ(ラピダス)や、グローバル大手・TSMC熊本工場への出資が挙げられる。これらは、自動車用高性能チップ(特に電動化・自動運転分野)の国内生産割合を高め、海外の地政学リスクや需給逼迫への対応力を増すものとなっている【3】。
■3. 通商政策・経済安全保障の強化
政府は、経済安全保障推進法や新たな通商協定(CPTPP、日EU・EPAなど)の枠組みを通じて、半導体・ハイテク素材の調達多角化を法的・制度的に裏付けている。また、関税の低減、投資保護、共通規格化といった施策で多国間の経済パートナーとの結びつきをより緊密にし、サプライチェーンの「単一故障点(single point of failure)」リスクを軽減している【1】。
■4. サイバーセキュリティ・災害対応ストラテジー
半導体製造現場や自動車工場は、自律化・IT化の進展に伴ってサイバー攻撃の標的となっている。これに対し、国の指針のもとでOT(Operational Technology)セキュリティ強化や、災害等によるサプライチェーン断絶リスクへの分散体制の強化が進められている【9】【7】。例えば国内複数拠点化や部材在庫最適化、迅速な回復力を持つ情報共有システムの導入などは、パンデミックや自然災害、政治的リスク発生時にも短期間で生産回復できる体制を意図している。
■5. 意義と今後の展望
こうした重層的戦略によって、日本の自動車産業は「ワシントンや北京が障壁を高めても、ネットワーク内のパートナーへ商流を付け替えられる」柔軟さを備えることを目指している【1】。グローバル経済の変調、脱炭素社会へのシフト、新興国需要の拡大といった外部環境変化の中、レジリエントで持続的なモビリティ産業基盤の確立が大きな社会的課題である。
まとめると、日本の自動車産業の半導体安定供給戦略は、政府と産業界が一体となり多元的サプライチェーン網を構築し、素材確保・生産分散・セキュリティ強化・多国間協調を総合的に展開することで、地政学的・経済的ショックに強い産業体質の確立を進めている点が特徴的である。その究極の目標は、「どの国でどんなショックが発生しても、サプライチェーンが致命的に途絶しない、自動車製造を安定持続できる」ことにある。